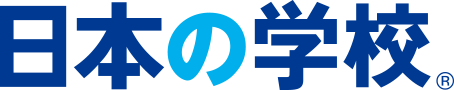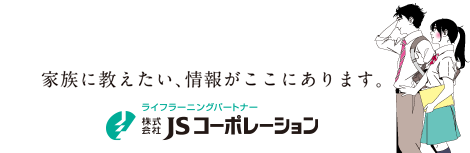■学部
●造形学部
●造形構想学部
■学費(2024年度)
初年度納入金:1,928,000円~1,958,000円
※学部・学科により異なります
※こちらの情報は2024年4月に学校公式HPより収集した内容になります。最新の情報は学校公式HPをご確認ください。
●造形学部
●造形構想学部
■学費(2024年度)
初年度納入金:1,928,000円~1,958,000円
※学部・学科により異なります
※こちらの情報は2024年4月に学校公式HPより収集した内容になります。最新の情報は学校公式HPをご確認ください。