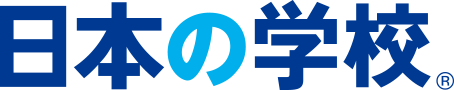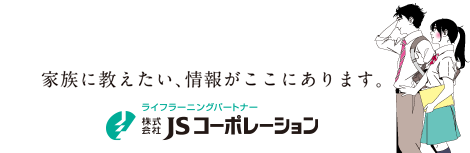- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
- 日本の学校 >
- 大学・短期大学(短大)を探す >
- 群馬医療福祉大学 >
- 学部・学科・コース一覧
パンフをもらおう
※資料・送料とも無料
群馬医療福祉大学の 学部・学科・コース一覧
専門知識・技術だけじゃない、人として信頼される専門職を育成
社会福祉学部 (4年)
- 社会福祉学科
- 社会福祉専攻
- (社会福祉コース)
- (福祉心理コース)
- (学校教育コース)
- 子ども専攻
- (児童福祉コース)
- (初等教育コース)
看護学部 (4年)
- 看護学科
リハビリテーション学部 (4年)
- リハビリテーション学科
- 理学療法専攻
- 作業療法専攻
医療技術学部 (4年)
- 医療技術学科
- 臨床検査学専攻
- 臨床工学専攻
群馬医療福祉大学の 学部・学科・コース一覧
専門知識・技術だけじゃない、人として信頼される専門職を育成
| 募集学部・学科・コース名 |
|---|
■社会福祉学部(4年)
|
■看護学部(4年)
|
■リハビリテーション学部(4年)
|
■医療技術学部(4年)
|
群馬医療福祉大学の所在地/問い合わせ先
●群馬医療福祉大学 社会福祉学部・医療技術学部(前橋キャンパス)入試広報センター
〒371-0823 群馬県前橋市川曲町191-1TEL.027-253-0294 FAX.027-254-1294 フリーダイヤル 0120-870-294
●群馬医療福祉大学 看護学部(藤岡キャンパス)
〒375-0024 群馬県藤岡市藤岡787-2TEL.0274-24-2941
●群馬医療福祉大学 リハビリテーション学部(本町キャンパス)
〒371-0023 群馬県前橋市本町2-12-1前橋プラザ元気21内 6・7階TEL.027-210-1294
スマホで見るsmartphone
スマホで群馬医療福祉大学の情報をチェック!